夏きらめく北アルプス日本三大雪渓の一つ 白馬岳から栂池まで縦走3日間ツアーでした(^O^)
2022年8月3日
2022/ 7/30〜8/1 白馬岳(2932m)3日間ツアー (データ:歩行距離16、3km、累計標高差+2014m−1442m、所要時間(休憩含)13、5時間)
北アルプス白馬岳に夏山のにぎわいが到来している。日本三大雪渓の一つ。白馬大雪渓を経由する人気のルートでは、登山者が涼しい風の中、列になって山頂を目指す。コロナ禍ではあるが山小屋の入り込みは少しずつ戻っているようだ。下界は真夏日が続いているが此処だけは別天地、白馬大雪渓を吹き下ろす涼風は15度位だろうか。雪渓を過ぎてからが「花の百名山」と云われるほど高山植物の宝庫でもあり、黄色のミヤマキンポウゲや青紫色のチシマギキョウ、だいだい色のクルマユリなど色とりどりの花が私たちを楽しませてくれた。

4年ぶりの白馬岳ツアーご参加ありがとうございます😊 前日は善光寺お参りして、白馬村の民宿でボリュームたっぷりに料理に満足。そして翌朝は、猿倉登山口まで送っていただきました。お天気も良し、今日は最高の登山日和になりそうです。

やっぱり人気の白馬岳ですね。猿倉荘前は早朝から登山者で賑わっています。

砂防工事専用道路を登って行くと、真っ青な空と峰々が待ち構えたように見えてきました。

小一時間ほどで白馬尻小屋の広場に到着です。

ここからの眺めはいつ見ても最高ですね。もう少し登ると大雪渓になります。

今年も白馬尻小屋は営業しておりません。と云うか、建物自体も組み立てていません。コロナ禍の影響なんでしょうか。朝食を摂ってから(トイレ有り)出発します。

日本三大雪渓のひとつ、白馬大雪渓歩きが本コースのハイライトです。アイゼンを装着して安全登山に努めましょう。雪も締まっており軽アイゼン、チェーンスパイクでもOKでした。

大雪渓は約2時間半くらいかかりました。途中、急勾配の箇所もありましたが、絶景に癒されながらの雪渓に大満足だったでしょうか。

お猿の軍団も仲間入りでーす 笑。

ようやく雪渓に別れを告げ、振り返ると登山者の列が続いています。

ここから小雪渓までお花畑が広がっています。しかし、岩場や渡渉、そして急勾配に汗ばむ皆さんです。

クロユリも見つけたよ^_^


この辺でひと休みしたーいとリクエストありました 笑。ハッカハッカ息が切れる。

ウルップソウ

タカネシオガマ。ご参加の方に調べて頂きました。


兎に角、珍しい花がたくさん咲いていますね。

上記の撮っていただいた画像が、同期されず横向きになっていますがごらんくださいね^_^


壮大な景色。少しずつ稜線に近づいてきています。



ここが最後の難関箇所をトラバースです。

岩場から村営山頂宿舎までが辛い登りですね。

ようやく白馬山荘が目の前に見えてきましたU^ェ^U

そして何よりのご褒美は、雷鳥の出現です(^_^)もっと近くに寄ってくれ 笑。

天気予報って当たるんですね。午後から雨模様ということで早出をしてきましたがおかげさまで大丈夫でしたが、午後からはガスって立山連峰から穂高連峰、富士山も見ることが出来ません。楽しみは明朝に取っておこう。

期待のレストランスカイプラザ白馬はコロナ禍で縮小営業でした。缶ビールでひと息つきました。

翌朝は予定通り東の空が明けてきました。ここからは八ヶ岳や富士山に方向だ。

北アルプスの全貌が少しずつ現れてきた。

午前6時。さぁ、白馬岳山頂を目指して出発します。


白馬岳山頂から歓喜の声が響きます 笑。それにしても雲海がきれいに広がっています。


お天気に恵まれて、ようやく待望の白馬岳を踏破しました\\\\٩( ‘ω’ )و //// おめでとう御座います🎉


小蓮華山まで2時間、今日は軽快な稜線歩きが待っていました。

振り返ると白馬岳から五竜岳と後立山連峰が望むことが出来ます。

お花も綺麗です


眼下には白馬大池が見え始めました。山荘で一休みして行こう。


うん、何と\(//∇//)\ 白馬山荘でコロナ陽性が出たらしいです。

白馬大池付近のお花畑も癒されますね。


乗鞍岳を過ぎてから雪渓をトラバースして、kさんが苦手な岩場を200m位下ります。そろそろ疲れが溜まっているでしょう。もう少し頑張って👍

ようやく木道に出ましたが、栂池高原駅まであと60分。昨日から16kmの山旅も終わりに近づいています。

最後に、夕方、白馬村の民宿からの絶景です。
今回のツアーに諸事情でキャンセルされた方は本当に残念でした。おかげさまでお天気に恵まれた白馬岳縦走ツアーになりました。ご参加頂いた皆さまありがとうございました。
実例の遭難事故から学ぶ。知っておきたい山のリスクマネジメント‼︎
2022年8月3日
本来なら、7月の南アルプス聖岳から光岳縦走ツアー報告したかったのですが、遭難事故に遭遇し今回はツアーを断念しました。参加者が枯れ葉で滑りバランスを崩して8mくらい滑落したが、幸いにも軽傷で自力で登山口まで戻ることが出来ました。山の遭難事故の多くはちょっとしたことから引き起こされる。標高の高低に関係なく、どんな山にもリスクは存在すると思います。登山計画を立てるときも実際に行動するときも「この場所にはどんなリスクが潜んでいるのか」を考えることが、危険回避につながっていくと改めて思いました。 今回のツアーを振り返ると、コロナ禍で聖平小屋、茶臼小屋など3泊分の食料が加わりザックが普段より重く、急勾配のつづら折りの狭い登山道が続く、それに加えて登山開始直後からの豪雨と云う悪条件が重なりました。奥深い秘境南アルプスの聖岳と光岳の4日間の歩行距離46km、累計標高差4225mの日本屈指の上級者コースでもある。遭難事故は何故起きたのか?体力や疲労、油断や不注意などの人的要因、雨や風など気象的要因、急勾配の狭い登山道が雨で緩んでいたなどの地形的要因を考えると、私自身の細かい注意指示が徹底してなかったのか。ガイドツアーも参加者がいればと云う安易な判断で催行したのではないかと自問自答する日々が続いています。
今回のツアーを振り返ると、コロナ禍で聖平小屋、茶臼小屋など3泊分の食料が加わりザックが普段より重く、急勾配のつづら折りの狭い登山道が続く、それに加えて登山開始直後からの豪雨と云う悪条件が重なりました。奥深い秘境南アルプスの聖岳と光岳の4日間の歩行距離46km、累計標高差4225mの日本屈指の上級者コースでもある。遭難事故は何故起きたのか?体力や疲労、油断や不注意などの人的要因、雨や風など気象的要因、急勾配の狭い登山道が雨で緩んでいたなどの地形的要因を考えると、私自身の細かい注意指示が徹底してなかったのか。ガイドツアーも参加者がいればと云う安易な判断で催行したのではないかと自問自答する日々が続いています。
私が思うには”危険“のなかでも最も危険なのは、その危険を察知できないことにある。問題なのは、何が危険なのかわからない、危険をシュミレーションできない、危険なことを危険だことだと考えられないと云うことだと思います。もし「自分は大丈夫」だと思っている登山者がいたとしたら、逆に、その人はかなり危うい遭難者予備軍にひとりだと云えるでしょう。
東北の名峰 鳥海山は裾野が日本海まで続き兎に角大きい‼️ 遥か先から望め威風堂々と聳えていました。
2022年7月12日
2022/ 7/ 9〜10 鳥海山(湯ノ台コース)ツアー データ:歩行距離12km、累計標高差1,253km、所要時間(休憩含)9時間半)
鳥海山は山形県と秋田県にまたがる標高2,236mの活火山です。秋田では出羽富士と呼ばれ親しまれている。山形では庄内富士と言われている。何れにしても存在感のある鳥海山に変わりない。ここ数年、秋田県側鉾立から登ってきたが、御室小屋はコロナ禍によりシュラフ必要と云うことで、山形側の心字大雪渓と展望、そして百花繚乱の変化に富んだ湯の台ルートを選択しました。宿泊地の山小屋滝ノ小屋の管理人菅原さんの心温まる対応に安らぎ、美味しいカレーライスと早朝発にも用意して頂いた朝ごはんに感激です。そこから始まる山行は最高の一日となりました。来年も花の百名山 鳥海山に来ようと思います 笑。

初日は湯ノ台登山口から30分登ったところにある、滝ノ小屋まで。管理人の菅原さん、そして奥様。アットホームな雰囲気の山小屋です。

持ち込みの冷たいビールでさっそく懇親会のはじまりです。再会や初めてに参加された方も直ぐに馴染んでいました。カレーライスも美味しく頂きました。

翌朝は、いざ鳥海山をめざして5時出発。すぐさま雪渓があり、ガスっていて夏道を探すのにひと苦労でーす。

八丁坂を1時間登れば河原宿小屋(廃墟化)到着。この辺りの湿原帯を過ぎると大雪渓登りが待っています。

河原宿のトイレは水洗で綺麗でしたよ。

万年雪の心字大雪渓(残雪の様子が「心」の字に見えることから、しんじせっけいと呼ばれている)は、左側を通り、小雪渓は右側を登るのがベストと聞いたが、ガスっていて視界が悪いし、結局はあざみ坂入り口まで雪渓が続いていた。今年は雪が多いようだ。

元気モリモリ(^O^)

河原宿から90分後に稜線直下のあざみ坂入り口に到着。ようやくガスも抜けてきました。


振り返ると、大雪渓に全貌が明らかになりました。有名な心字雪渓の姿を目にすることができました。

湯ノ台登山口の急所!雪渓を登りきると、鳥海山屈指の急坂あざみ坂があります。そして、あざみ坂を登りきると、外輪山の伏見岳となります。目の前のある新山ドームはガスってまだ見えません。

ここから七高山手前の分岐まで稜線上を歩いていきます。お花畑が疲れを癒してくれます。


少しずつ雲が流れ、展望が広がる。鳥海山に来て良かったと実感する。

一旦、ザレ場を下り雪渓をトラバースしてから、新山に登るのだが慎重をきする通過点でもある。


例年より兎に角雪が多いと感じる。


岩が重なる不安定な箇所を過ぎると鳥海山山頂だ。


秋田側の日本海が望むことができた^_^

鳥海山(2,236m)は燧ヶ岳に次いで東北地方で2番目に高い日本百名山です。

遠方からご参加いただいた皆さま。待望の鳥海山の嶺に立つことができましたね。お天気も味方してくれました。

大物忌神社は準備中でお札を買うことができませんでした(//∇//) ここで昼食を摂ってからぜ下山します。登り5時間、ここまで予定通りに行程時間です。


外輪山を歩く登山者の姿が見えました。

ヨツバシオガマが

チョウカイフスマでーす(^_^)

一気にあざみ坂を下りました。最高のお天気になりました。

山肌にはニッコウキスゲの群生地が。

アイゼンを装着して大雪渓を下ります。

景色が広がる大雪渓をルンルン🎶。鳥海山最高でーすv(^_^v)♪

午後2時無事に登山口に下りる。大変おつかれ様でした。これから、鳥海山荘温泉♨️で疲れを癒して帰りましょう。


















































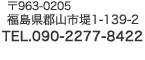

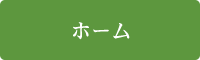
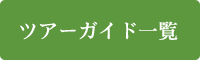
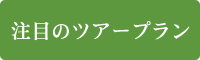
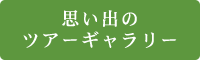
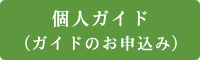
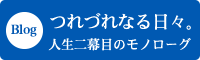

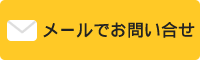


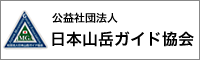
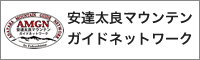




 今回のツアーを振り返ると、コロナ禍で聖平小屋、茶臼小屋など3泊分の食料が加わりザックが普段より重く、急勾配のつづら折りの狭い登山道が続く、それに加えて登山開始直後からの豪雨と云う悪条件が重なりました。奥深い秘境南アルプスの聖岳と光岳の4日間の歩行距離46km、累計標高差4225mの日本屈指の上級者コースでもある。遭難事故は何故起きたのか?体力や疲労、油断や不注意などの人的要因、雨や風など気象的要因、急勾配の狭い登山道が雨で緩んでいたなどの地形的要因を考えると、私自身の細かい注意指示が徹底してなかったのか。ガイドツアーも参加者がいればと云う安易な判断で催行したのではないかと自問自答する日々が続いています。
今回のツアーを振り返ると、コロナ禍で聖平小屋、茶臼小屋など3泊分の食料が加わりザックが普段より重く、急勾配のつづら折りの狭い登山道が続く、それに加えて登山開始直後からの豪雨と云う悪条件が重なりました。奥深い秘境南アルプスの聖岳と光岳の4日間の歩行距離46km、累計標高差4225mの日本屈指の上級者コースでもある。遭難事故は何故起きたのか?体力や疲労、油断や不注意などの人的要因、雨や風など気象的要因、急勾配の狭い登山道が雨で緩んでいたなどの地形的要因を考えると、私自身の細かい注意指示が徹底してなかったのか。ガイドツアーも参加者がいればと云う安易な判断で催行したのではないかと自問自答する日々が続いています。
































