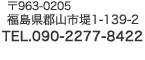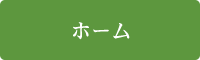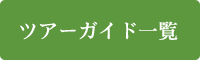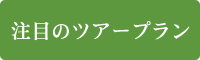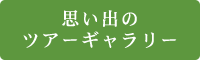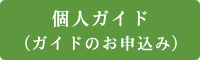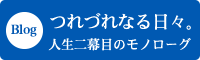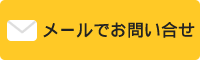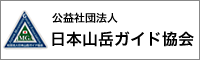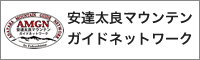大雨がやんだ後も、登山道の崩壊や土砂災害に警戒しよう!
2025年7月15日
停滞前線「居座り豪雨」後の「登山のリスク」と「危険ポイント」
大雨がやんだ後も、登山道の崩壊や土砂災害に警戒しよう!
停滞前線の特徴は、とにかく長期間、日本列島に居座るということ。気温が高い夏は高温多湿な空気の流入によって前線の活動も活発で、広い範囲で強い雨を降らせている。雨により山の土も水をたっぷりと吸って地盤が緩むことが想定される。大雨の後は、登山のリスクが高くなる。近年は大雨の後に落石や土砂崩壊が起きることが増えていて、山頂付近での急斜面が崩壊し、登山道が一時通行止めになったりもしている。
沢沿いや雪渓なども大雨の後は注意が必要な場所だ。登山を予定している方は、歩くルートの地形的な特徴を把握し、想定されるリスクに備え、安全登山を楽しんでください。
気象庁によると、前線が停滞する原因について、太平洋高気圧の勢力が弱いこと、偏西風の流れにより前線が日本列島に下がってきたことが可能性として考えられるという。太平洋高気圧は、夏の天気を見るうえで重要なポイントの一つ。高温多湿な空気を持つ太平洋高気圧は、まさに夏という季節の支配者だ。その勢力範囲によって、日本付近の天気も大きく変わってくる。
太平洋高気圧の勢力が弱まり、日本がちょうど高気圧の縁に当たると、高気圧の縁を回り込んで北上する台風や暖湿流により、大雨などがもたらされやすくなる。夏に天気図を見る時は、ぜひ高気圧の勢力範囲にも注目してみましょう。
日本列島に豪雨被害をもたらす「線状降水帯」とは? 山や沢での強雨の危険
梅雨末期、「線状降水帯」による被害が相次いだ日本列島。一カ所で降り続く雨により土砂崩れや浸水などの被害が報じられた。今回は線状降水帯の仕組みを紹介。また、これから暑い夏を迎えるが、強雨や大雨で起きやすい山や沢での危険も知っておこう。
■線状降水帯とは

積乱雲が線状に連なって大雨を降らせる「線状降水帯」。7月7日7時のレーダー画像(出典=気象庁ホームページより)
7月に入ってからの山陰地方や九州南部での大雨の原因として「線状降水帯」が注目されている。(実例)
線状降水帯とは、文字通り、帯状(線状)に強い雨が降っているエリアのことだ。一カ所で強い雨が長時間降り続くので、土砂災害や河川の氾濫など大きな災害が起きやすくなる。

線状降水帯の発生の仕組み
線状降水帯は、積乱雲が連なって次々に流れ込んでくることで起きる。上の図のように、海から暖かく湿った空気が流れ込み、前線や山岳などの影響でそれが急激に上昇すると、そこで積乱雲が発達する。
通常は、その場で積乱雲によって強い雨が降る。積乱雲は比較的寿命が短いので、数時間で強い雨は収まることが多い。
しかし、線状降水帯の場合は、積乱雲が上空の風に流され、風下に向かって流れていく。続けて海からの暖かく湿った空気が流れ込み、ぞくぞくと積乱雲の発生が続くので、強い雨を降らせる線状降水帯ができる。
■強雨や長雨の後は、山の土も崩れやすくなる
![]() 長雨の後、たっぷり保水した土は軟らかく、雑草もすぐに抜ける
長雨の後、たっぷり保水した土は軟らかく、雑草もすぐに抜ける
線状降水帯では、同じ場所に強い雨が降り続くため、降り始めからの総雨量が大きくなる傾向にある。
豪雨でなくても、雨が長時間降り続ければ、土はたっぷりと水を蓄積し、崩れやすくなる。たとえば、庭や畑の草むしりで、晴れ続きの日に渾身の力を込めても抜けなかった雑草が、長雨の後だとスルッと抜ける。保水した土がどれだけ軟らかく、脆くなるのか少し想像できるだろう。
大雨が降っているときに登山をする人はまずいないだろうが、大雨や長雨のあとも警戒してほしい。落石が起きやすい崖沿いや沢沿いのほか、雪渓などは急激に雪解けが進んで地盤が緩み、土砂崩落などが起きやすい状態となる。雨がやんだ後も、数日は十分に警戒が必要だ。
■気を付けたい水の事故
これから日本列島は、暑い夏の季節を迎える。梅雨明け後はこれまでのような長雨の日は減り、晴れる日が増える予想だが、湿った暖かい空気や、上空の寒気の影響で、短時間の強い雨や雷雨の日がありそうだ。気温は平地でも30℃以上になるところが多く、蒸し暑い日が続く見込み。
これからの季節は、沢登りや登山シーズンだが、ここ数年、山でも水の事故が目立ってきている。

増水が早い沢と増水が遅い沢、どっちがどっち?
突然だが、クイズに挑戦してみよう。上の図で、Aのような形の沢と、Bのような形の沢、どちらが増水しやすいだろうか?(黒線は山の稜線、青線は沢を表現している)
答えはA。上流に支沢が何本もあり、下流で一カ所に集まるような沢は、すぐに増水するうえ、たとえ大雨でなくても増水しやすい。「雨が降り出して驚くほど早く水かさが増してきた」などという話も、よく聞くヒヤリハット体験談だ。
沢登りなど本格的な登山でなく、下流の渓谷ぞいのハイキングの場合も、注意したい。自分の出かける沢がどんな形をしているのか、どんなリスクがあるのか事前に調べて考えたうえで出かけよう。年々、雨も極端な降り方が増える傾向にあり、地形の複雑な山岳地帯では、より状況の判断が難しくなる。無理をせず、安全第一で夏の山を楽しみたい。
(線状降水帯関連記事より抜粋)
「花の名山」と呼ばれる白山は、爽やかに咲き競う高山植物が兎に角すごかった!クロユリや馬ノ立髪ニッコウキスゲの群落も印象的でしたね。
2025年7月8日
2025/ 7/4〜6 白山2702m(御前峰)ツアー データ:歩行距離12,6km・累計標高差+−1516m・2日間の所要タイム13時間(休憩含む)・コース(別当出合から砂防新道で室堂・翌朝山頂に登り、花と展望の観光新道で下山するメイン周回コース)
石川・岐阜・福井・富山の四県にまたがる「白山(はくさん)」は、御前峰・大汝峰・剣ヶ峰などの山々の総称。日本百名山にも選ばれていて、古くから信仰の山として親しまれてきました。白山は7月1日からいよいよ夏山シーズンが始まりました。白山山系は他山系から隔離された独立山系です。そのため白山には他の山岳からとび離れて分布しているいくつもの豊かな高山植物群が、全250種類超え約100種の分布の西限になっています。夏の白山は「花の名山」と呼ばれるほど、随所に美しい花が咲き誇る。7月初旬から8月上旬にかけては特に花の見ごろと言われており、白山を代表する「クロユリ」や「ハクサンコザクラ」「ハクサンチドリ」などの群生が白山室堂周辺で間近で見られるのが楽しみですね。今回のツアーは、花の白山トレッキングを堪能してから金沢での滞在も大いにエンジョイしましょう。

早朝4時に郡山市を出発してから約7時間かけて白山の主要登山口である市ノ瀬ビジターセンター経て別当出合に到着。予定通り12時から白山室堂に向けて登山開始です。

奥深い山岳地に位置する白山には原生的な自然が残る地域であり、石川・富山・岐阜・福井にまたがる白山国立公園に指定されている。周囲の山々を見上げると、なんかワクワクして来るようです。

別当出合休憩舎から吊り橋を渡って行くと、登り専用の急な石段があり、転倒しないように注意が必要です。なんだか最初から急なのでハッカハッカして辛いけど頑張りましょう。

出発から30分で中飯場。一気に汗だくの皆さま。ゆっくり休憩してから次のポイント別当覗へ。

ピンクの色に咲いたタニウツギが満開です。花から呼び出した雌しべが目を引きますね。磐梯山や安達太良山でも見られます。



高度を上げていくと少しずつ展望がひらけてきます。



甚之助谷を見上げると、大規模な地滑り補強工事が行われている様子がうかがえます。




花弁状の白いガク片が特徴的なサンカヨウ。とても良い香りがするサンカヨウでしたね。この辺でたくさん見かけました。


大きな花を傘のように広げる、キヌガサソウ。群落しているようです。

4月下旬はいわきの二つ箭山に登ったとき堪能した、ムラサキヤシオがまだ咲いているんです。さすがに3000m級の山です 笑。


甚之助避難小屋までの鞍部には雪が残っていました。このぐらいだったらつぼ足で大丈夫でしょう。

残雪の湿地には必ず咲いている、紅色のショウジョバカマです。


先頭の私は踏み抜きをしてしまった。名誉の負傷?左太腿に響く。

ここまで順調に登ってきまた。甚之助避難小屋に到着です。ここまで標高差700m・時間にして2時間半くらいかかったかな。暑さも幾分なくなり涼しくなった感じです。ここからが正念場です。

多少ガスってきたが、歩きやすいお天気になりました。樹木もまばらになり別山方面が眺められるようです。

まだヤマザクラが咲いていましたね。

イワカガミの登場です。


まだまだ余裕のある皆さま。黒ボコ岩までは急勾配なので足元注意です。





まさに命の水場です。延命水で後5年頑張りましょう。






十二曲り一帯のお花畑に癒されながら、眺めの良い(今回は視界ゼロ)黒ボコ岩分岐に到着。この先は、御前岳を仰ぎながら弥陀ヶ原の木道歩きになります。室堂まであと少しですよ。

弥陀ヶ原は主として湿地の植物が多く、数年に一度コバイケイソウの開花群落が見れれるそうです。また、クロユリ、ハクサンコザクラ、ハクサンフウロ、イングルマ、イワイチョウ、ミヤマキンバイ、ミヤマガラシ、アオノツガフウロ、ミネズオウなどそのその時々に応じて木道沿いに見れれるそうです。


最後の五葉坂をひと踏ん張りで、今夜の山小屋室堂に着きます。ようやくお天気も回復してきましたね。

おつかれさまでした。只今の時間5時40分。ギリ夕食時間に間に合いました。もちろん生ビール🍺待っていてくれました。ありがとうございます。

標高2450mにある白山室堂にも夕焼けが始まりました。最高峰の御前岳麓の水屋尻雪渓とのコントラスト見事でしょうか。

7時を過ぎることろに陽が沈みます。星空も輝いていたそうです。明日のおお天気が下り坂で心配です。おやすみなさい💤。

おはようございます。早朝5時から最高峰の御前岳を目指します。予想通りといいうか生憎のお天気でので、御池めぐりはやめてピストンしてから室堂に戻ります。

さっそく、クロユリを見つけて大興奮です。室堂平では自然観察路が設けられています。今年は例年より残雪が多く若干開花が遅いようなかんじでしょうか。






山頂には奥宮の社が鎮座し、神職の万歳で日の出を迎えるようです。





本来でしたら、北アルプス連峰や乗鞍岳・御嶽山をはじめ、遠くは八ヶ岳や南アルプスまでの大展望が楽しめるもですが残念です。それでも霊峰白山を登頂した達成感に大満足のようですね。


御朱印をいただいてから朝飯にしましょう。2時間歩いたのでお腹が空きましたね。

お腹も満たしたら、別当出合まで下山しましょう。きょうも花の白山を堪能しましょう。

少しずつですが青空が見え始めたようです。ワクワクしますね。さて、帰りのルートはどうしましょうか。観光新道はお花畑と尾根歩きでの展望がいいのですが、がれ場や谷筋の急坂が心配です。


それでも黒ボコ岩か分岐から観光新道ルートを選択しましょう。蛇塚を過ぎた辺りからお花畑が広がっていました。ニッコウキスゲやハクサンシャジンなどが混生する馬のたてがみ・真砂坂一帯は、この道ならではの美観でしょうか。自然が作りだす色鮮やかな絨毯のような花々に、ただ感動。誰に世話されたわけでもないのに、毎年、見事に花を咲かせるのはなぜだろう? ハクサンコザクラ・ハクサンフウロ、白山の名を冠した高山植物は全部で18種類もあるそうです。確かめてみてくださいね。



























夢のような時間を楽しんだ稜線歩きを終え無事予定時間に別当出合に戻ることができました。ご参加いただきありがとうございました。さて、今夜は金沢市に宿泊してノドグロを食べましょう。明日の観光と近江市場でのお鮨も楽しみですね。
なぜ磐梯山のまわりには、美しい景色や猪苗代湖、檜原湖、五色沼湖沼群などの湖や沼があるの?
2025年7月8日
初夏の平日、磐梯山ジオパーク裏磐梯エリアの景勝地を訪ねる。風光明媚で魅力的な自然をたのしみつつ、大地と人と共生の歴史を知り、広く世界に伝えていくことは、私たちのみならず、未来をになう子供たちのためにも、きわめて重要なことと言えましょう。

きょうは裏磐梯五色沼自然探勝路を毘沙門沼まで湖沼めぐりです。ここだけは涼風が爽やかで別天地のようです。片道約90分お付き合いください。

ここは国立公園の特別保護区に指定されている高原エリアです。つたうるし、最初に現れた柳沼は、透明な鏡のように綺麗でしろやなぎのようです。

ここ五色沼からは裏磐梯山を見上げると、磐梯火山の崩壊壁と銅沼(あかぬま)の風景です。磐梯山は今から137年前の1,888年に起きた水蒸気噴火によって、磐梯山北側にあった小磐梯という山が崩壊を起こし、その際生じた岩なだれによって、川がせき止められ桧原湖や大小300以上の美しい湖沼を生み出しました。標高1,100mにあるカルデラ湖あかぬまを水源とする、五色沼湖沼群は磐梯山ジオパーク人気の景勝地です。

1,888年の噴火で荒廃した国有地にアカマツを中心に杉や漆など植林をした遠藤現夢の碑がある。磐梯における観光の先駆けと言えるかもしれない。



るり沼、青沼、弁天沼は銅沼系湖沼と呼呼ばれている。湖水は多量のカルシウムと酸性イオンを含み、青く澄んだ美しい沼です。

これらの湖底にはウカミカマゴケやホソバスギゴケが繁茂し、るり沼では大きいもので直径10m,高さ5mにも及ぶこけのマットが湖底を埋め尽くしている。






弁天沼からは吾妻連峰が見渡せました。


丸まった形の不思議な葉っぱを見つけた。「オトシブミ」という虫が、卵をクヌギの葉っぱに産んで包んでゆりかごなんですよ。とても小さな虫だけど卵を守るために工夫しているんです。

モリアオガエルの卵かな

次々の現れる湖沼の色のコントラストの変化を感じながら歩いて来ました。最後の毘沙門沼は五色沼の中で、周囲四km、深さ13mの最大の沼でした。
磐梯山噴火で生まれた環境とそこで暮らす生き物たち!
磐梯山の北側には、明治の噴火によって流れ山地形た多くの湖沼が誕生しました。そこでは、地形や水位などの違いによって、湖沼や川などの「水辺」、湿原やヨシ原などの「湿地」、ヤナギやハンノキなどが茂る「茂った林」、」さらに流れ山にアカマツなどが根を下ろした「若い林」など、変化に富んだ植物の生育環境があります。噴火から百数十年という時間の流れの中で、植物群落の遷移を見ることができます。また、」噴火の影響をまぬがれたブナを中心とした「安定した森」、磐梯山南麓など古くから人間の活動でつくられた「農耕地」という環境もあります。こうした多様な環境には、それぞれに適した多様な植物が根付き、それらの植物を好む多種の野鳥・昆虫・魚類・両生類・ほ乳類などが暮らし、きわめて多くに種類の植物や動物が育成、生息する生態系が形成されています。磐梯山がもたらした大きなお宝のひとつでしょうか。

長雨の後、たっぷり保水した土は軟らかく、雑草もすぐに抜ける