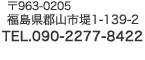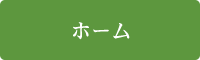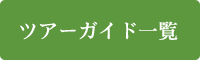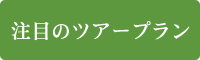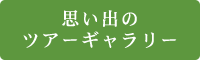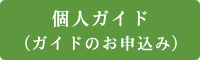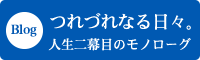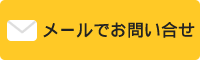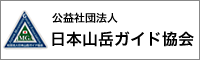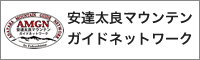ガイドの四方山話≫一覧を見る
- 2026/2/2 大変お待たせしました!冬の安達太良山は標高2,000m以下とは思えないほどの山岳景観が広がる魅力的な山でした。
-
2026/ 2/1(日) 安達太良山ツアー データ:歩行距離9,4km・累計標高差789m・歩行タイム5:45(奥岳登山口ピストン)
今季最強寒波が長期的に影響が続く冬型の気圧配置が日本海側に大雪をもたらしています。安達太良連峰も降雪は少ないが最長寒波で山頂付近はこのところ爆風が続いているようです。雪山のリスクは前日に沢山の積雪があった場合はラッセルで思うように進まず途中撤退も強いられることもあります。もちろん冬山での強風は体力が消耗するだけでなく危険が伴います。ギリギリまで様子を見てルートファイデングを検討しながら判断することになります。今回のツアーは、寒波で気温が低いがここ数日は積雪が少なく山麓の天気予報は曇りで登山指数Bということで催行に至りました。

朝方は雪が舞ったようだが穏やかな1日になりました。皆さんが無事に安達太良山に到達することを朝焼けに願つつ自宅を出る。

予定通り8時半には奥岳登山口から薬師岳経由で歩き始まる。ちょっと登山道から外れたお地蔵さんに朝の挨拶して出発しましょう。

やっぱり山頂付近はガスっているようですね。私たちが山頂にたどり着く頃お天気が回復して展望が開けるといいのですが。


出発から1時間20分後に薬師岳山頂に到着。此処からは街並みが見渡せるようでした。

氷点下の世界では樹林に白い花が咲いているように幻想的です。


最後の急坂を登り切ると安達太良山がまもなくです。最後の力を振り絞り頑張りましょう。

皆様お疲れ様でした。安達太良山に到着です。ここから突起物のような山頂まで登りますよ。

冬の安達太良山を制覇されたご気分はいかがでしょうか。飯豊連峰や磐梯山、蔵王連峰は残念ながら見ることができませんでしたが、言いようのない達成感がいっぱいかと思います。

クレーターのような沼の平火山源まであと僅かでしたが、このような天気なので次の機会にご覧くださいね。稜線上にできたエビの尻尾はいかがでしたか。如何に安達太良山は風強いかがイメージできたでしょう。



このポーズは雪山ならでしょうね。

皆様のご協力いただき安達太良山ツアーを無事に終えることが出来ました。ご参加ありがとうございました。帰りは岳の湯♨️で1日の疲れを癒してから解散です。
- 2026/2/2 パワースポットでもある達沢不動滝は冬の撮影人気スポット。静かにそして力強く流れる滝からは、荘厳さが漂います。
-
2026/ 1/31 逹沢不動滝スノーハイキングツアー
安達太良山系船明神山に源を持つ不動川にある滝です。中ノ沢温泉街から車で10分ぐらい林道に入ると冬場は誰も入らない達沢不動滝に続く原生林がある。ここから40分ぐらい歩くと達沢不動滝に到着する。「ふくしま緑の百景」に選ばれた原生林はミズナラを主体とした多数の植物で構成されており、センノキ・シナノキ・ミズキ・イタヤカエデ・アカマツ・トチノキ等の老古大樹が森林の自然形態をそのまま残っています。途中から達沢川に変わり猪苗代湖に流れ出る。冬場は訪れる人の少ない原生林に囲まれた信仰の地の名爆を求めてのスノーハイキングツアーです。

今日は沼尻高原ロッジに泊られた、タイのインフルエンサー達の案内で達沢不動滝まで行ってきました。

たくさんのスノーシューを積み込んで現地まで先導します。

集落を過ぎたところ除雪がなくなります。夏場だったら達沢不動滝まで歩いて10分くらいですが、ここからだと40分くらいかかります。

幸いにも今日は青空に恵まれた1日になりました。PR用の撮影が進みそうで安心です。


急斜面を下りて沢すじに走り去るカモシカの足跡が生々しいですね。


日本海側は豪雪というニュースが連日流れているが、この付近はまだ雪が少ないようです。スノーシューも必要ないようです。

達沢不動滝に続く一本沿いの原生林と沢すじの景色が素晴らしいです。ここからも登れそうです。


まもなく達沢不動滝に到着のようです。








達沢不動滝は、安達太良山系船明神山に源を持つ不動川にある滝です。高さ10m、幅16mにわたり、一枚岩の黒い岩肌を一枚のカーテンのように流れ落ち、その飛沫が本流にかかる豪快な「男滝」と、そのすぐ下流にひっそりとたたずむ優美な「女滝」からなります。


ドローンでの撮影もありました。俯瞰からパーンしていくと素晴らしい画像が撮れるようです。

男滝は水量が多いせいか部分的に凍結していたが、女滝は完全に氷瀑しているようです。



撮影の合間におやつタイムです。沼尻名物の笹団子と猪苗代湖で採れた浮草をお茶にした「菱茶」を召し上がっていただきます。

約3時間の行程でしたが無事に終えることが出来ました。お疲れ様でした。




明日は安達太良山ツアーです。今のところ何とか大丈夫なようです。帰りは中ノ沢温泉♨️に寄って帰ります。
- 2026/2/2 冬の絶景を求めて〜今年も樹氷をめぐる蔵王連峰への山旅は、寒波の影響により残念ながら途中での不本意な撤退となる。
-
2026/ 1/24~25 樹氷の蔵王連峰熊野岳ツアー
1月初旬からは冬型の気圧配置が続く蔵王連峰の山域ではあったが今年は特に類を見ない寒波が停滞しているようでした。ここ一週間は悪天候が続いたせいか誰も登っていないのでトップゲレンデのスタート時からラッセルを強いられることになりました。少しずつルートファイデングして登っていくが強風と寒さで思うように進まず途中タイムアップ。ある程度、天候に恵まれると熊野岳までのルートは大勢の登山者が樹氷を巡りながらトレッキングを楽しめる筈でしたが、行く先は視界不良で安全を考えたら撤退という選択肢になりました。それでも焼き肉屋で米沢牛を堪能したり上杉謙信ゆかりの地を観光するなどの2日間の山旅でした。

ロハスハイキング恒例となったライザワールドスキー場から登る冬の蔵王連峰ツアーにご参加いただきありがとうございます。今日は焼き肉さかので米沢牛を食べてから、上杉謙信ゆかりの地観光です。米沢市内もここ一週間で積雪があったようです。

かつて米沢城の本丸があった上杉神社でお参りしていきましょう。そのあとは上杉14代目の私邸上杉伯爵邸を廻ります。




画像が飛びますが、かみのやま温泉宿で♨️三昧で過ごして、翌朝、蔵王連峰の登山口であるライザワールドスキー場に向かいました。旅館での気温はマイナス5度。さすが雪国だと思いながら道路も凍っていて寒かったですね。スキーヤーで賑わっているが館内は登山者装備をした人が少なくツアー参加者が数組くらいのようです。それでもリフトを乗り継いでトップゲレンデへ。この辺りは風は感じないが視界不良のようです。まず始めにスノーシューを装着しましょう。


スタート時から視界不良のこんな状態です。やはり登る人は少ないないようです。それでもカップルが後ろから付いてきましたが、早々と撤退したので前後には誰1人いない山行となりました。

この先から左手に回り込み上っていくのですが、ルートは積雪のためトレースはないのでざっくりと方向を決めて歩くので時より膝までのラッセルが続きます わら。

ビックモンスターはスタート時から次々と現れてきます。


標高が上がってくると強風と寒さが襲ってくるようです。普段はあっという間に行けそうな避難小屋辺りで残念ながらタイムアップです。振り返ると安達太良山から朝日連峰までの展望を見てもらえなかったのが残念ですが、ここで撤退します。お疲れ様でした。この後、スキー場を下りましたが、強風と寒さがより厳しい天候となりました。

ライザワールドスキー場駐車場での気温はマイナス7度。たぶん登山中は氷点下マイナス15度くらいだったようです。

下山後は、かみのやま温泉♨️共同浴場で温ったまりました。よねざわ道の駅のラーメンを美味しかったですね。今回はピークハンと敵わず残念でした。ほんとうに遠方からのご参加ありがとうございました。